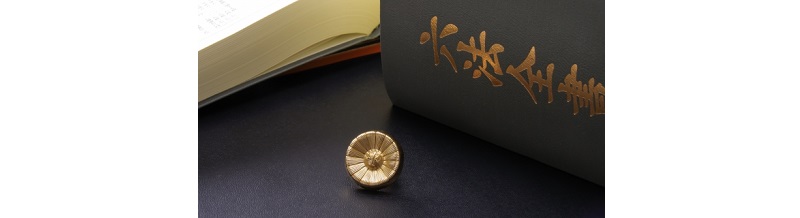キャバクラ営業に直接関係する風営法の最新改正内容(2024年~2025年)について、重要なポイントを現場目線でわかりやすく解説します。
◆キャバクラは「風俗営業1号」に該当
まず前提として、キャバクラは法律上、「風俗営業1号」(接待を伴う飲食店)に分類されます。
業種法的区分主な要件キャバクラ風営法 第2条第1項第1号接待・飲酒・深夜営業・照明・構造設備などが規制対象。そのため、風営法や条例が改正されると、キャバクラ営業は直接影響を受けます。

「接待行為」の定義がより明確化
風営法における「接待行為」の定義が明確化された内容について、2024年以降の最新の行政運用を踏まえて詳しく解説いたします。
特にキャバクラやガールズバーなど“接客を伴う飲食業”に従事する方に関係が深いポイントを中心にまとめます。
◆風営法における「接待行為」とは?
風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)において、「接待」とは、“客を歓楽させることを目的として、個別に特別なもてなしをする行為”を意味します。
この「接待」に該当するかどうかが、風俗営業の許可が必要か否かの判断基準になります。
◆なぜ「定義の明確化」がされたのか?
背景:
- バー、コンカフェ、ラウンジなど“許可なし”の飲食店で実質キャバクラ営業が横行
- 一部の自治体で判断にばらつきがあり、「グレーゾーン」が温存されていた
- 風営法違反の摘発件数が2022〜2023年で全国的に増加
- 接待の基準が曖昧で、事業者・警察双方にとって判断が難しかった
こうした背景から、2023年末〜2024年にかけて、警察庁が“接待行為の具体的内容”を明文化・統一的に運用する方針を示しました。
◆明確化された「接待行為」の代表例(2024年以降)
以下のような行為は、原則すべて「接待」に該当し、風俗営業許可が必要です。
行為接待に該当する理由
- 客の隣に座って会話を続ける
個別に継続的な“もてなし”と判断 - 一緒に乾杯・お酒を飲む
私的な関係性を演出する行為 - タバコに火をつける/ライターを渡す
特別な配慮=もてなしと判断 - ボディタッチ(肩を叩く・手に触れるなど)
肉体的接触による親密さの演出 - おしぼりを膝に置く・上着をかける
飲食サービス以上の対人サービスと見なされる - 客の話に深く共感し、長時間付き添う
特別扱いと判断される可能性がある - 撮影・SNS投稿に応じる
特別な接遇として記録が残る行為
◆グレーゾーンの排除:曖昧だった行為も“接待”とされるように
従来:
「ちょっと話すだけなら大丈夫」「カウンター越しならOK」など、“場所”や“形式”で判断されることが多かった。
現在(2024年以降):
→ “行為の実質”で判断する方針に変更。
たとえカウンター越しでも、継続して個別対応を行っていれば「接待」とみなされる可能性があります。
◆接待に該当しない行為(合法)
- 飲食の注文を取る→通常の接客行為
- お冷や・料理を配膳する→業務上のサービス
- 会計の案内をする→店舗運営上の案内
- 軽くあいさつや短時間の会話→特別扱いでなければセーフ
- 店内案内(席までの誘導など)→一般的なホール業務
これらは「接待」には該当しませんが、“笑顔で案内しただけ”でも、会話の長さや親密度次第で接待とされることもあるため要注意です。
◆許可の要否と実務的な注意点
| 状況 | 許可の必要性 |
|---|---|
| スタッフが客の隣に座る/長時間話す | 風俗営業1号許可が必要 |
| カウンター越しでも会話が長時間/特定客に偏る | 実質接待と判断される可能性あり |
| 無許可で接待行為をしていた場合 | 無許可営業(風営法違反)で摘発対象 |
※無許可で接待行為をしていた場合は無許可営業(風営法違反)で摘発対象となります
◆従業員・キャストの教育で押さえるべきポイント
- 「接待=笑顔・話し相手」ではないと認識させる
- お酒を勧めない/一緒に飲まない
- 隣に長時間座らない(回転を意識)
- お客様への“個別サービス”はすべて接待とみなされ得ると理解する
- 「よくある行為だから大丈夫」は通用しない時代へ
◆まとめ:今後の接待行為は「実質+継続性+対人性」で判断される
- 客を楽しませる・満足させることが目的かどうか
- 対象の特定性特定の客にだけ親密に接する場合は接待と見なされやすい
- 継続性1回限りよりも、繰り返されることで“営業行為”と判断されやすい
- 営業と無関係かどうか
- SNSでのDMなども「接客の延長」とされるケースがある
キャバクラ、ガールズバー、コンカフェなど“接客付き飲食店”の運営者は、今後ますますこの「接待行為の定義」を軸に、営業スタイル・教育・許可管理を見直す必要があります。

従業員名簿・管理者責任の厳格化
風営法における「従業員名簿」と「管理者責任」の厳格化について、特にキャバクラ・ラウンジ・スナック等の営業者が知っておくべき最新の運用ポイント(2024年以降)を中心に、詳しく解説いたします。
◆背景:なぜ「名簿管理」や「管理者責任」が厳格化されたのか?
背景には以下の3つの流れがあります:
- 無許可営業・未成年雇用などの法令違反が全国で多発
- SNSや短期バイト経由で身元不明のキャストが増加
- 事件やトラブル発生時に「誰が働いていたか不明」というケースが多数
これにより、警察庁は2023年末~2024年にかけて、全国の生活安全課を通じて「名簿の記載・管理責任の徹底指導」を通知。従業員の記録管理を“営業許可と同等に重要視”する時代に突入しています。
◆【1】従業員名簿に関する最新の規制内容
◼ 名簿の作成・保存は法的義務(風営法施行規則 第38条)
氏名(本名)
通称・源氏名のみでは不可
生年月日
年齢確認のため、免許証などで裏付け必須
住所
現住所を正確に記載(虚偽は違反対象)
雇用開始日・退職日
正確な記録がなければ、監査で是正指導
業務の種類
ホール係、接客担当など役割を明記
身分証の写し原本確認+コピー保存が推奨される(免許証・マイナンバー等)
保管期間:
→ 退職から3年間の保管が必要(これを怠ると指導・営業停止命令の対象になることも)
◆【2】管理者責任の強化ポイント
風俗営業許可には、「営業所ごとに管理者1名の選任」が義務づけられています(風営法第11条の2)。
2024年の運用改定で、「名義貸し」「実態なし管理者」への指導が全国で強化されました。
◼ 管理者に求められる3つの義務
- 常駐義務:原則として営業時間中は常駐(名ばかりの管理者はNG)
- 教育・監督責任:違法接待・未成年雇用・名簿不備などに対して責任を負う
- 管理者講習の受講:都道府¥県が主催する講習会を1年に1回必ず受けることが義務付けられている
◼ 違反した場合のペナルティ
違反内容主な処分例
- 名簿不備:行政指導 → 是正命令 → 営業停止の可能性
- 無講習・虚偽報告→風営法違反として営業許可取消や更新拒否のリスク
- 未成年の深夜勤務→管理者の個人責任(刑事罰含む)が問われる場合あり
◆現場でのよくあるNG例
- 登録せずに1日体験をさせる→従業員扱いになるため
- 名簿未記載=違反「友人だから」と身分証確認を省略
- 年齢不明・身元不明者の雇用は重大な違反
- 管理者が不在で営業
- 管理者の常駐義務違反 → 即営業停止命令もあり
- 源氏名のみで記録法的には“実名記録”が必須条件
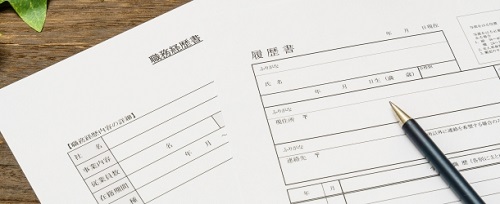
深夜時間帯の「照度」や営業形態の指導強化
風営法における「深夜時間帯の照度(明るさ)」や「営業形態」に関する警察・自治体の指導強化の動きについて、特に2024年以降の改正・運用変更を踏まえて詳しく解説します。
キャバクラ、バー、ガールズバー、ラウンジ等の飲食業と接客の“境界線”にある業種にとっては、極めて重要なポイントです。
◆背景:なぜ「照度」と「営業形態」が問題視されているのか?
近年、以下のような店舗が全国で増加していることが、監督強化の背景にあります。
- 「バー」として届出しているが、実際はキャバクラに近い接客を行っている
- 「深夜酒類提供飲食店」の許可のみで、午前0時以降も密着接客を継続
- 店内を意図的に暗くし、接待行為が目立たないようにしている
これに対して、警察庁および各都道府県警察は2023年〜2024年にかけて、実態に即した取り締まりと照度管理の厳格化を打ち出しました。
◆照度(店内の明るさ)に関する指導強化ポイント
◼ 照度とは?
照度とは、店内の明るさ(単位:ルクス)のことです。
風営法では、「薄暗い照明」=“接待行為の隠ぺい・密接な関係性の助長”と判断されやすくなります。
◼ 基準値:10ルクス以上
警察の指導における最低基準は「10ルクス以上」です。 明るさの目安イメージ5ルクス以下キャンドルライト程度(薄暗く、顔がはっきり見えない)10ルクスカフェの読書灯よりやや暗いレベル30ルクス以上居酒屋や家庭用リビングの明るさ
◼ 違反と判断される例
- 客席を意図的に暗くし、接待が視認できない構造にしている
- カウンター奥だけ照明が落とされており、密接な会話が可能
- 照明調整をスタッフが自由にできる構造になっている(=監視困難)
これらの店舗は「営業形態が風営1号に該当するのに、届出営業で深夜接待を行っている」とされるリスクがあります。
◆営業形態に関する運用強化(2024年以降)
◼ よくある指摘パターン(実例)
- 「届出ではバーになっているが、店内の照度が極端に低い」
- 「店員が客の隣で10分以上会話し、ドリンクを一緒に飲んでいた」
- 「女性スタッフが席を回って乾杯・指名対応していた」
→ これらは“風俗営業1号に該当”と判断され、届出営業では違法になります。
◆アドバイス:店舗の現状チェックリスト(簡易版)
- 店内で10ルクス以上の照明が常時維持されていますか?
- 深夜0時以降、スタッフが隣に座って会話していませんか?
- 女性スタッフが乾杯・ドリンクを勧める行為はありませんか?
- 警察の立ち入り調査を想定したルール整備・記録はありますか?
→ 一つでも「No」がある場合、運営の見直し・許可区分の再確認をおすすめします。

SNS・ネットを使った「営業行為」への警告強化
1. 背景と問題点
キャバクラ・ホストクラブなどの店舗では、従来の路上勧誘やビラ配りに加えて、 SNS(Instagram、Twitter、TikTok、LINEなど)を使った営業が主流となっています。
しかし、これらの中には、以下のような違法・不適切とされる行為が含まれているケースがあります。
- 店舗の営業を目的としたDMによる未成年者への勧誘
- 個人アカウントを使った無許可での客引き行為
- 不特定多数への性的な暗示を含む投稿(風営法違反にあたる可能性)
- 営業許可のない個人による「無店舗型営業」(出張接客など)
2. 警察・行政による最近の動き
- 警察庁から全国の生活安全課に対し、「SNSによる勧誘行為」への指導・取締り強化の通達(令和4年以降)
- 東京都、大阪府などの都市部では、ネット監視強化とともに、摘発例も増加
- アカウント運用に関するガイドラインを業界団体と協議しながら整備中
3. 違法とされる行為の具体例
| 違反内容 | 該当する法令 | 罰則例 |
|---|---|---|
| 未成年者へのDM勧誘 | 青少年健全育成条例、風営法 | 50万円以下の罰金や営業停止処分 |
| 営業許可のない「個人営業」 | 無許可営業(風営法第3条違反) | 2年以下の懲役または200万円以下の罰金 |
| ネット上での過剰接待の示唆 | 公然わいせつ、風営法違反 | 刑事罰、SNSアカウント停止措置 |
4. 実務対応・SNS運用での注意点
- スタッフに対し、SNS上の言動規制とルールを教育・明文化する
- 店舗公式アカウントの投稿内容は、業務内容の宣伝に限定し、誤解を招く表現を避ける
- 未成年と疑われるアカウントからのDM・フォローは一切返信しない
- 警察・行政からの指導があった場合は速やかに削除・謝罪対応を行う
5. 今後の動向とまとめ
今後、行政によるガイドライン策定やSNS企業との連携も進み、さらに取締りが強化される見込みです。
特に未成年保護と無許可営業の防止を重視した対応が求められており、「ネットだから大丈夫」という認識は危険です。
経営者・管理者は、従業員のSNS活動を正しく監督・指導できる体制を整えることが重要です。

都道府県ごとの動きにも注意
風営法の運用における「都道府県ごとの条例や行政運用の違い」に焦点を当てて、特にキャバクラやラウンジ、ガールズバーなどの経営者・運営者にとって重要な視点を整理し、2024年以降の最新動向を踏まえて詳しくご紹介いたします。
なぜ「都道府県ごとの動き」に注意すべきか?
風営法は全国共通の法律ですが、実際の運用は各都道府県(公安委員会・生活安全課)が条例を通じて独自のルールを設けているため、地域によって“できること、できないこと”が大きく異なります。
また、最近は以下のような背景から、条例や行政指導レベルでの規制強化が相次いでいます:
- 観光地化・再開発に伴う住民との摩擦(新宿・渋谷・中洲など)
- 未成年雇用・深夜営業・無許可営業の摘発件数の増加
- SNS・アプリ等を通じた“店外営業”への取締強化
◆都道府県別:注目すべき具体的な動き(2024年〜)
【東京都】
深夜営業規制と再開発エリアの出店制限が焦点
- 午前1時以降の通報制度導入(住民通報→行政調査ルート確立)
- 豊洲・虎ノ門・麻布台など再開発地区における「出店ガイドライン」厳格化
- 店外営業(SNS・LINE)に関する実態調査と条例化検討中
- バー型キャバクラ営業への立入調査(照度・接客監視)を常態化
注目エリア: 新宿歌舞伎町、渋谷センター街、豊洲、虎ノ門、麻布台
【大阪府】
ミナミ地区の集中指導と「違法キャッチ」根絶に注力
- 違法スカウト・キャッチに対し、大阪府警が重点摘発継続中
- 飲食店を装った接待営業(実質キャバクラ)への摘発件数が増加
- ミナミ周辺の「無届営業」実態調査が強化
- 一部地域で営業許可の新規取得が難化傾向
注目エリア: ミナミ(難波・心斎橋)、北新地、十三
【福岡県】
中洲エリアの健全化と多言語対応強化が進行中
- 中洲エリアの風俗営業許可更新の審査が厳格化
- 海外客の急増に伴い、「外国語表示のガイドライン」を導入
- 路上キャッチ行為への警告回数が増加
- 巡回指導を月次で実施(立入調査の頻度も上昇中)
注目エリア: 中洲、天神、博多駅周辺
【愛知県(名古屋市)】
錦三丁目エリアを中心に、風営許可の再審査が強化
- 錦三での「無許可接待行為」への警察指導が増加
- 道路使用・路上スカウト対策の条例強化を名古屋市が検討
- 午前2時以降の営業店への調査件数が倍増傾向
- LINE営業・同伴強制のトラブルに対する相談件数が増加中
注目エリア: 錦三丁目、栄、大曽根
【北海道(札幌市)】
すすきの地区で「デジタル通報制度」の試験運用開始
- 地域住民がスマホアプリ経由で深夜営業店を匿名通報可能
- 行政と連携し、違法営業店舗の情報収集と調査を効率化
- 風俗営業と飲食店の線引きがあいまいな店舗への重点監視
- 店舗照度の基準見直し(営業形態の“偽装”防止)
注目エリア: すすきの、大通、狸小路
【京都府】
風俗営業の歴史的制限区域(祇園・先斗町)に新ガイドライン導入
- 観光地と風俗営業の“共存”を重視し、営業形態に関する細則を追加
- 地元住民と連携し、深夜営業の制限時間を超える店舗の監視を強化
- 店舗の外観・看板・照明基準に対する規制が強化中
注目エリア: 祇園、木屋町、先斗町、河原町
【沖縄県】
観光需要の回復に伴い、国際通り周辺の無許可営業の取締り強化
- 深夜営業店の営業届出漏れ・風営法違反が多発
- 観光地での「キャッチ型営業」「店舗案内所」の管理強化
- 外国人観光客トラブル防止のため、英語・中国語対応も強化傾向
注目エリア: 那覇(国際通り・松山)、北谷、宜野湾
◆地域ごとの違いが出やすい項目一覧
① 【風俗営業許可の取得難易度】
- 違いが出る理由:
各自治体の警察署や保健所の審査基準・運用に差があるため。 - 差が出やすい地域:
東京都(港区・中央区)、京都市(祇園周辺)、福岡市(中洲) - 例:
同じ業態でも、渋谷では比較的通りやすいが、虎ノ門では実質許可が下りにくい。
② 【深夜営業(午前0時以降)の規制運用】
- 違いが出る理由:
深夜酒類提供飲食店の扱い(風営法ではなく飲食店営業許可)に対する監視体制が異なるため。 - 差が出やすい地域:
札幌市、名古屋市、大阪市(ミナミ)、東京都(豊洲・銀座) - 例:
東京23区内でも、エリアによって午前1時以降の“実質指導”の強さに差がある。
③ 【照度(店内の明るさ)基準の運用】
- 違いが出る理由:
接待行為の有無を判断する材料として「照度基準」を厳密に運用する地域と、形式的に済ませる地域がある。 - 差が出やすい地域:
東京都(特に新宿区・中央区)、京都府、北海道 - 例:
札幌では“バー”名義でも照度基準が曖昧だと立入調査対象になるケースが増えている。
④ 【キャッチ・スカウト行為への対応】
- 違いが出る理由:
条例で明文化されているかどうか、また警察・自治体の取り締まり頻度に差があるため。 - 差が出やすい地域:
大阪(ミナミ地区は特に厳格)、名古屋(栄・錦三)、東京(渋谷・新宿) - 例:
大阪ミナミでは「立っているだけで指導対象」になる一方、地方都市では黙認されている例も。
⑤ 【再開発エリアでの出店制限】
- 違いが出る理由:
都市再開発計画の内容と地元住民・企業との調整結果による - 差が出やすい地域:
東京都(虎ノ門・豊洲・麻布台)、福岡市(博多駅再開発周辺) - 例:
豊洲ではマンション住民の反対により、深夜営業店の出店がほぼ不可能になりつつある。
⑥ 【SNS営業・店外営業に対する規制の動き】
- 違いが出る理由:
条例で“営業”の定義にSNSを含むかどうかが自治体により異なるため。 - 差が出やすい地域:
東京都(特に新宿区・豊島区)、愛知県、福岡県 - 例:
一部自治体では「LINE営業」や「インスタ経由の店外誘導」が問題視され、実態調査が始まっている。
⑦ 【未成年との接触に関する指導・罰則】
- 違いが出る理由:
補導件数、相談件数、SNSの監視体制が各県で異なるため。 - 差が出やすい地域:
東京都、埼玉県、大阪府、福岡県 - 例:
SNS経由での“店外デート”を通報された場合、都内では行政処分に直結するケースがある。
◆まとめ:「全国どこでも同じ」は通用しない。地域に応じた適法運営を。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 都道府県の条例に沿った運営が前提 | 法律より“条例と運用”が実態を左右する |
| 出店・業態変更時は慎重に調査 | 用途地域・立地・近隣施設の確認が不可欠 |
| 警察との信頼関係が営業の土台 | トラブル前の相談が、最も重要な「予防策」 |
| SNS・出勤情報の発信も対象に | 「店外の行為」も営業と見なされる可能性がある |